書道教室へ
- 2013年12月10日 (火)
年賀状の文字「福壽」の練習に行ってきました~
息子の中学生時代の習字道具を持ってね。
筆を持つのは、もしかして 高校2年生以来?
だとしたら、36年ぶり? (>_<)
しかしながら、半紙の前に座ると、シャンとした気持ちになりました。
「福壽」「能作幾代」のお手本が 向うにチラリと見えますね。
美しい~ この様に うまく書けたらなぁ ・・・
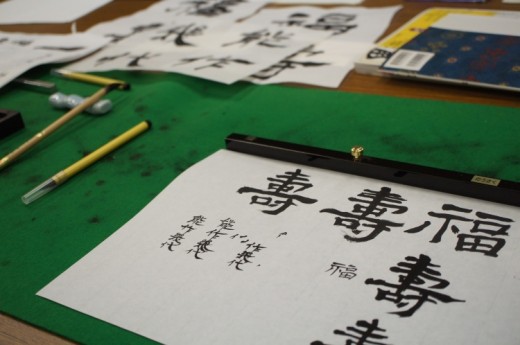
先生 は、nousaku のお客様の女流書道家さん。
わがままを言って この6文字だけの練習です。
隷書体は横長なのに、「壽」という文字は横の画数が多くて
縦長になってしまいます。 (-_-;
あっという間に1時間半。
集中が切れて、ダメだぁ~
あとは 家での練習ということで。
この私が 家で習字が出来るのだろうか?と
不安ではありますが、年賀状だから 今月中には
やり終えるでしょう。(笑)
- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0
私の書斎
- 2013年11月24日 (日)
ご近所にある図書館は、そんな存在です。(笑)
明日までに、紅色を決めないといけないのですが
それが 本職ではない私には、参考資料がありません。
それなら、とりあえず 図書館で関係書を探そう!
そんなわけで、バタバタの日でしたが 合間に図書館へ。
色の本を探すはずが、他の興味のある本にも
当然ながら、目が行きます。
今日は、この 3冊を。
「隷書のすすめ」・「洛中洛外図 – 舟木本」・「日本の伝統色」
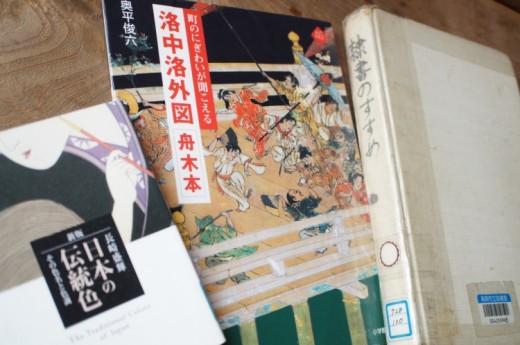
せっかく選ぶなら 日本の伝統色から。
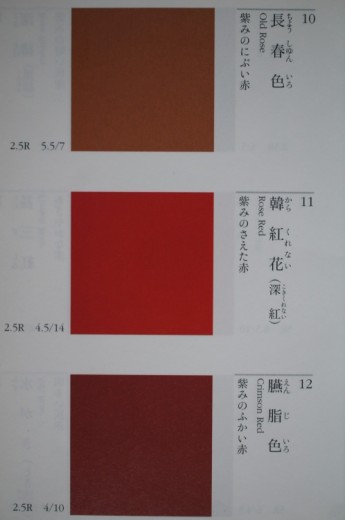
先日 東京国立博物館で見たばかりの「洛中洛外図- 舟木本」
博物館では、大勢の人でゆっくりと見れなかったし、
双眼鏡でも持っていないと見れないくらいとても小さかったから
本で確かめたい~
五条大橋のお花見時期の様子。
両脇から支えられる酔っ払う人あり、桜の花を持って楽しそうに踊ってる人あり
ひとつひとつが 目に止まります。
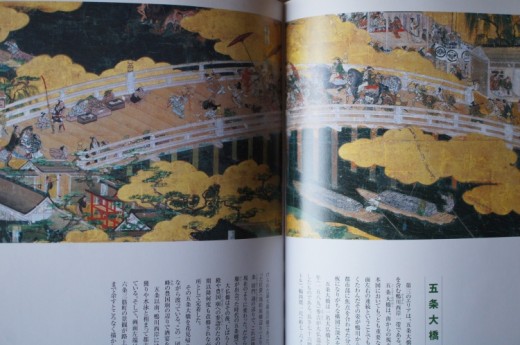
「空海」を読んだ後なので、「東寺」も気になります。
この洛中洛外図は、東寺の五重塔からの景色が基本という説があるそうです。
この世の「聖と俗、表と裏」を描いています。
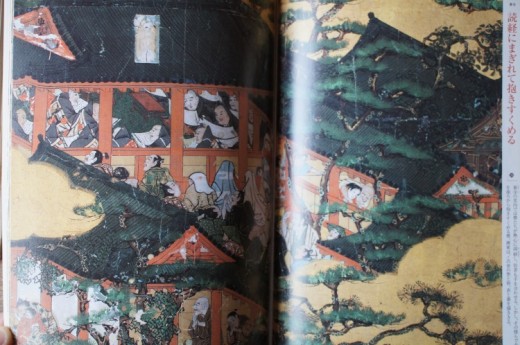
MYブームの「隷書」も。
自分の名前も書けたらと「 能 作 幾 代 」という漢字を 探し出しています。
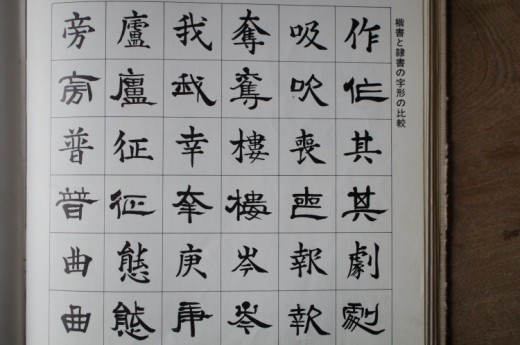
しかし、本を見てるだけで書けるわけもなく ・・・
さっそく、習字の先生に「隷書」のみ、それも「福寿」と「能作幾代」だけの
レッスンの申し込みをいたしました。
なんという のめり込みの性格か!
レッスンの様子は、また後ほど。
まだまだ 本を読みたいところですが、事務処理に追われています。 (-_-;
- BLOG | 本 | 習いごと・研修・資格・大学 | 自己啓発
- Comments: 0
初めての料理教室
- 2013年06月30日 (日)
去年の9月 に母に教えてもらおうと思い
はや、9ヶ月。
やっと、初めての料理教室が終了。
「茗荷寿司」と「胡麻豆腐」がメイン。
「南蛮漬け」、「浅漬け」、「いちぢくワイン煮」も。
セッティングは私の役目。
どうしようかと悩んだ結果、初夏のイメージで。
竹籠にガラス、染付の器です。

各自が 自分のお寿司を握ります。
寿司飯が 手にいっぱい くっついたりで 大変!

胡麻豆腐の「辛し味噌」も手作りで。
母が用意した「黒い漆器」は、皆さんのお好みでしたね。

冷茶(冷酒では、ありません~)の「チロリ」や
敷き物の麻の「蚊帳」は、母が用意したもの。
「娑羅双樹」も 母が持ってきてくれました。

料理教室ということで、お料理の手順は もちろんですが、
室礼にからむ「器」や「花」などの準備も 大切なこと。
私は、それらを 母に改めて教えてもらいました。
- BLOG | nousaku 講座 | 室礼・建築・デザイン | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0
茶事のお稽古
- 2013年05月30日 (木)
文化ホールの大広間での「薄茶」や「お濃茶」「炭点前」などの
小間切れのお稽古ではなく、昨日は先生のお宅で 茶事のお稽古でした。
私は、亭主役をいたしました。
中門でご挨拶をして。

昼頃まで雨でしたので、露地笠をかぶります。
(イメージ写真です)

蹲に水を溜めたり、露地に水を打ったりと、
茶事の準備は初めてのこと。
風炉では、まず 持寄りのお料理での懐石から。
雨が上がり、青々としたお庭が綺麗でした。

初炭、菓子、中立。
軸を仕舞い、花を掛け、鐘鉦を鳴らして濃茶、後炭、薄茶、退席。
4時間もの時間、新しいことばかりで
頭も身体もパンパン。
「三露」「三炭」の講義も受け、茶事の奥深さを知ります。
先生のお宅のお庭を眺めながらの茶事は
日常を忘れ、癒される時間となりました。

月一回のホールでの稽古の他にも 先生のお宅での茶事も
しばらくの間、月一回開催されることとなりましたので
この機会にしっかりと茶事を習得したいと思います。
日頃は家での割り稽古に励まなくっちゃね。
袱紗裁きが、下手くそなんです ・・・ (-_-;
- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学 | 茶道・中国茶
- Comments: 0
金継ぎ
- 2013年04月28日 (日)
早いものです、もう 金継ぎ講座の日となりました。
今回は、またまたワンランク上に 挑戦します。
ガラスのお皿と、幾つにも割れた器。

作業は家で出来ますので、先生に手順の再確認。
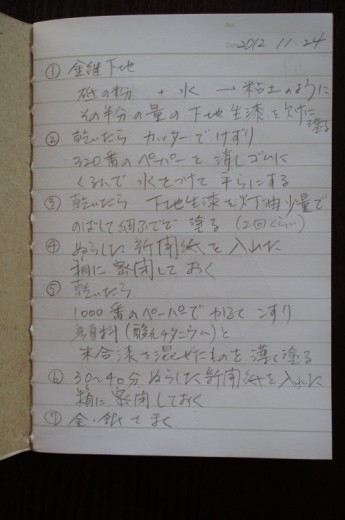
2週間前の「銀継ぎ」に引続き、今日は「金継ぎ」の出来あがり。
明るすぎて、見えにくいですね。
またの機会に アップでお見せしま~す!
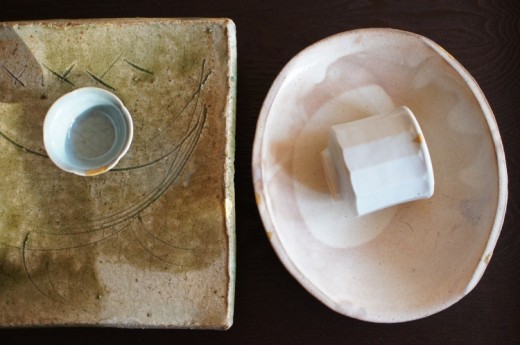
他にも 「金継ぎ」ではなく、漆器の相談も。
経年による ひび割れや くすみを 見てもらいました。
上から漆を塗ることとなり、次回の作業となります。

連休中は、家での 金継ぎ作業を 頑張りま~す!
- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0
銀継ぎ
- 2013年04月16日 (火)
1月の第4土曜日に やり始めた大物。
4月の第2土曜日に 4回目にして(2月はお休みしましたので)
やっとのことで 出来あがりました!

「黒田泰蔵」氏の向付。

「青木良太」氏の鉢。

「高桑英隆」氏の青磁の大鉢。

骨董の染付の小鉢。

今回は「銀継ぎ」でしたが、残りの器は、次の講座で「金継ぎ」予定。
継いだ器の方が愛着があり、よく使うようになりますね。
さて、今日も一日が始まります。
無駄の無いよう、計画を立てて!
- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0
目一杯
- 2013年04月11日 (木)
過去に数回 受講してる「富山大学 オープン・クラス」の
受講生募集要項が 郵送されてきました。
学びたい気持ちは ありますが、今の私は
あれこれと 自分から忙しくしていて、目一杯。 (:_;)
それでも、なんとかならないかしら?
まず、今日のやることを 書き出してみて
自分の時間に 余裕があるか見てみることに。
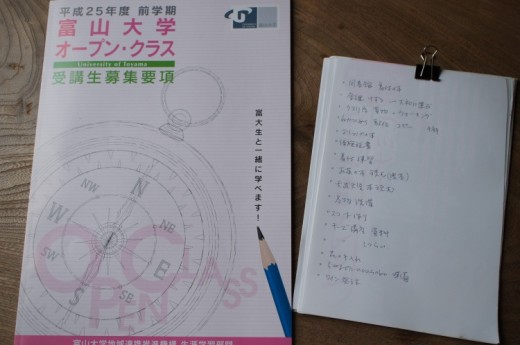
今日一日かけても、出来そうもない項目がズラリと。
書き出してない家事一般も 加えてあります。
やっぱり、「富山大学 オープン・クラス」は
あきらめるしかないですね ・・・ (:_;)
いつになったら、ゆっくり 出来るのでしょうか?
- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0
金継ぎ講座
- 2013年03月09日 (土)
今日は、第2土曜日、金継ぎ講座の日です。
午前中に、ワンピースを仕上げ、午後から 講座へ行ってきました!
2月は土曜日の都合が悪くて、一ヶ月ぶりの受講となり、お久しぶりです。
まずは、割れたお皿をくっつけるために
お昼に炊いた白米を持参し、練って「糊」にします!
そうですよね、昔は接着剤なんてありませんから。

糊と漆を混ぜ、お皿をくっつけます。

2週間後まで 乾かしておきます。
いつも慌ただしい私にとって、とても気の長い作業は
気を落ち着かせることにもなります。
「地に足を着ける」ような感覚です。
ちゃんとご飯を作ったり、テーブルセッティングで食事を いただいたり、
裁縫をしたり、本を読んだり ・・・
それら 全てが、私の安定に つながっているのですが
最近は、それらに振り回されて、本末転倒状態です。
まぁ、今日で裁縫も金継ぎ講座が 一段落しましたので、
あれこれと 首を突っ込むことを セーブしようと思います。
明日は、母と ゆっくりと過ごすことにしま~す。
- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学 | 自己啓発
- Comments: 0
第4土曜日は
- 2013年01月27日 (日)
金継ぎ講座です。
第2・第4の月2回の講座で、今回で5回目です。
今日から また新しい器の 金継ぎをやり始めます。
前回より 大物が多いです。

今日は 講座終了後に大和デパート7階の食堂にて 懇親会。
ちょうど 雪が止み、いいお天気に。
新湊大橋が 見えましたよ~

先輩方々と健康話に花が咲きました! (笑)
こんな時間の使い方は、久しぶりだなぁ ・・・
- BLOG | 器・金継ぎ | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0
金継ぎ その後
- 2012年12月23日 (日)
11月 第4土曜日 から習い始めた「金継ぎ」
昨日で、3回目となりました。
月に2回なので、なかなか 進んでいきません。 (:_;)
1回目は、砥の粉と生漆を混ぜたモノを 欠けた部分に塗り付けます。
2回目は、1回目で塗り付けた箇所を
カッターやサンドペーパーで、器の形に整えます。
昨日の 3回目では、整えた箇所に再度 生漆を塗り
湿らせた新聞紙を入れた箱に しまって帰ります。
次回 4回目で、金を蒔くのでは・・・と。
私のではありませんが、後ろの席の方の
銀継ぎとペーパーウエイトの蒔絵です。
銀継ぎもクールで素敵ですね♪

こちらは、別の方。
先生が お手本を 見せてくださいます。

まずは、金継ぎを完璧にしたい!
欠けたお皿が たっぷりあるので。 (-_-;
今日は、ちょっと 落ち着きましたので、
メール返信他、諸々を やろうと思います。
図書館へも 行ってこようかな~
- BLOG | 習いごと・研修・資格・大学
- Comments: 0